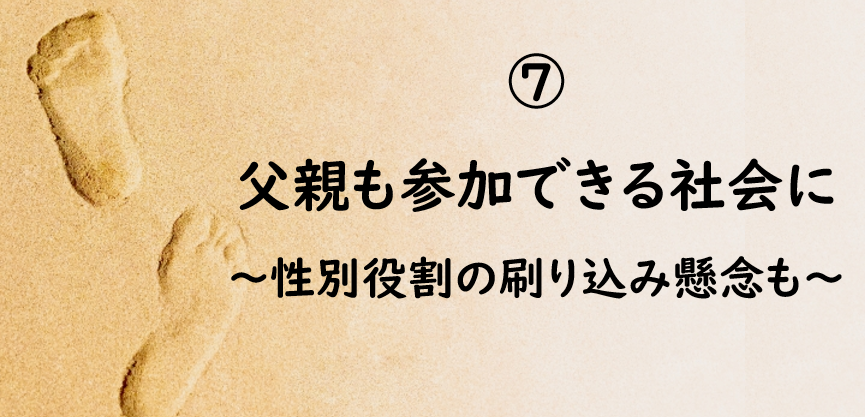PTAとは別に、「おやじの会」という集まりがあります。学校により名称は違いますが、主に父親が参加しており、私の知る限りでは休日のイベント開催や、運動会のテント設営などの力仕事で頼りにされています。「おやじの会のイベントで盛り上がった」といった声は多く、学校生活に間違いなく寄与しています。
PTAとは別に、「おやじの会」という集まりがあります。学校により名称は違いますが、主に父親が参加しており、私の知る限りでは休日のイベント開催や、運動会のテント設営などの力仕事で頼りにされています。「おやじの会のイベントで盛り上がった」といった声は多く、学校生活に間違いなく寄与しています。
ただ、子どもたちの目にどう映るかは大切な視点です。
PTAは、母親が家にいることが当然だった戦後に普及しました。当時から参加者の大半は母親で、今も父親の参加は少数です。しかし過半数が共働き世帯の今、平日に学校へ行くのが難しいのは、母親も同じです。
「おやじの会」があることで、父親と母親で役割が異なり、「週末遊んでくれるのはお父さん」「平日学校でお世話をしてくれるのはお母さん」と見えてしまう可能性があります。さまざまな価値観が形成され育まれる学校で、性別による役割分担が無意識のうちに刷り込まれるのは、決して望ましくありません。
一方、「おやじの会」の父親からは「子どものために何かしたいけど、仕事は休めない」と本音が聞こえてきます。子どもを理由に会社を休みにくい現状が、平日学校集合が多いPTAとは別に「おやじの会」を生み出しているのかもしれません。実際、コロナ禍で在宅勤務が増えると、学校の備品を消毒するボランティアなどに父親の参加が増えたそうです。
PTAは子育ての延長であり、社会の縮図です。オンライン化や負担軽減を進め、誰にとっても無理のない環境になれば「子どものために何かしたい」父親も参加できるはず。それがPTA本来の姿ではないでしょうか。
PTA専用支援サービス「ピータス」代表