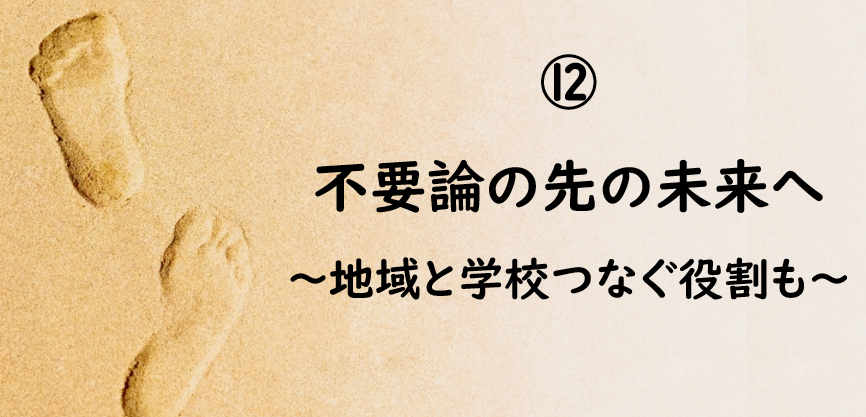コロナ禍を機に「やらなくてもいいこと」が顕在化し、PTA不要論さえ耳にします。PTAはこの先、どう進化していくのでしょうか。
コロナ禍を機に「やらなくてもいいこと」が顕在化し、PTA不要論さえ耳にします。PTAはこの先、どう進化していくのでしょうか。
これまでは学校生活のサポートが中心で活動の時間や場所が限定的でしたが、地域と学校のハブのような役割を果たすPTAが出てきました。
例えば、PTA主催のお祭りに地元企業や住民を巻き込んだり、地域の人々や企業に専用アプリをインストールしてもらい、発信端末を持った子どもを見守るサービスを導入したり。街全体で、子どもたちの成長と安心安全を支える空気づくりを主導しています。
また、学校と地域を橋渡しする地域コーディネーターと協働し、保護者ではない地域の人にも読み聞かせや職業人講話に参加してもらうなど、より多様な人たちが学校と関わる仕組みをつくっているPTAもあります。
保護者の意識も変わってきました。コロナ禍でお便りがオンライン化されたものの、当初は役員が決定事項を学校のメール配信システムを使って送るだけ、というPTAが多かった気がします。
しかし最近は、要望の聞き取りや対話の意向が高まり、保護者間でやりとりできるツールを望むPTAが増えています。
また、参加の仕方も多様に。これまでは無関心ゆえに言われるがまま参加していた人がほとんどでしたが、今は主体的に「賛同して会費だけ払う」という選択をする会員も出てきました。もちろん会費を払うだけでも、十分子どもたちへのサポートになります。
「未来」は日々の積み重ねです。たとえ小さく、迷いながらでも、踏み出せば必ず未来に近づきます。一歩ずつ、一緒に進んでいきましょう。
PTA専用支援サービス「ピータス」代表