「学校&教育UPDATE Group」秋季年会に登壇させていただきました


独立総合教育政策研究所(所長:安部慎也先生)とは、学校教育(主に小中高)を中心に、教育を社会全体で捉えた調査・研究・開発を行う、現役の先生が立ち上げた独立系の研究機関です。「学校・教育UPDATE Group」の講座企画・運営、教職員の相談・カウンセリング、機関紙『学びと教育』発行などを事業として行い、先生方や教育関係者の資質向上とネットワーク形成を目的に活動している団体です。
また、「学校・教育UPDATE Group」は、同研究所の主事業で、幼・小・中・高の先生や教育に関わる人が垣根を越えて参加するオンラインコミュニティ。ピータスも時折参加させていただいていますが、参加者同士が「UPDATE講座」や対話交流を通じて、常に実践や知見を“更新”しながら共有する、とてもポジティブで刺激的な学びの場です。
「学校・教育UPDATE Group」では、春と秋の年2回「年会」という大型のオンラインイベントが開催されます。内容は基調講演+複数の分科会(テーマ別発表・対話)で構成され、教育に関わる行政や現場・研究機関の方が登壇されます。
今回、9月23日に開催された2025秋季年会の「学校・PTA・地域とのつながり分科会」にてお話しさせていただけたことは、大変光栄でした✨
「PTAと協力して、校務も行事も楽しくラクちんに!」
9月23日に開催された第4回秋季年会では、基調講演として、文部科学省 文部科学審議官 矢野和彦先生から「日本の教育の国際化」についてお話を伺いました。
その後参加者が6つの分科会に分かれ、各登壇者から話を聞き、ディスカッションをするのですが、ピータスは第1分科会にて「学校・PTA・地域とのつながり」というテーマでお話しさせていただきました。
大変心強いことに、第1分科会のスーパーバイザーとして、前丹波市教育長をつとめられた岸田隆博先生がアドバイスをくださいました。岸田先生はPTA会長のご経験もあるため、参加者の先生方により共感をもって聞いていただけたのではないかと思います。
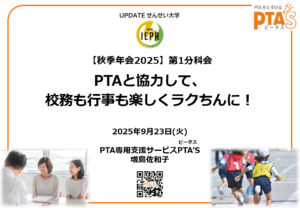 ピータスからは、PTAと学校が「対話」→「課題共有」→「解決手段の分類(活動/作業)」というステップで連携することの大切さ、双方の負担を軽減しながら、楽しく子どもたちの学びや安心・安全を高める実践例などを紹介させていただきました。具体例としては、旗当番シフト作成ツールの「面談調整」への転用、行事運営(警備・受付等)の外部委託、通学路の危険箇所をデザイナーが地図化する取り組みなどを提示させていただきました。
ピータスからは、PTAと学校が「対話」→「課題共有」→「解決手段の分類(活動/作業)」というステップで連携することの大切さ、双方の負担を軽減しながら、楽しく子どもたちの学びや安心・安全を高める実践例などを紹介させていただきました。具体例としては、旗当番シフト作成ツールの「面談調整」への転用、行事運営(警備・受付等)の外部委託、通学路の危険箇所をデザイナーが地図化する取り組みなどを提示させていただきました。
講評の中で岸田先生から、「PTAと学校が対等に」とコメントをいただきました。この言葉に、ピータスとして大変励まされましたし、参加者の先生方にとっても、身近且つ説得力をもって伝わったのではないかと思います。
ありがたいことに参加者の皆さんからは、岸田先生からの講評も含め、下記のような感想をいただきました。
●保護者と学校は対等な関係であり、子どもを軸に対話をすることが大切ということを学べました。
●子どものためになっている活動なのか、先生や保護者だからできる活動なのかを対話をしながら、活動を見直していくことが必要と感じました。改めて、ピータスのサイトじっくりみてみたいなと思いました。本日はありがとうございました。
●PTA活動は、学校にとっても保護者にとっても大きな意味を持つ一方で、「任意加入」であることが十分に周知されていなかったり、活動そのものが「子どものため」より「組織の維持」に偏ってしまったりする現実もあると感じました。また、教頭・副校長に負担が集中するなど、学校側にしわ寄せがいってしまう構造的な課題も見えてきました。
●保護者と学校が「対等に話す」こと、そして「課題を共有する」ことが持続可能な活動のカギだという点に深く共感しました。保護者の視点が「我が子だけ」にとどまると共感や協働は難しくなりますし、学校側が「学校はこうあるべき」と固定的な姿勢をとっても対話は成立しません。互いの立場を尊重することで初めて前進できるのだと思います
一方で、PTAだからこそできる企画や、外国籍保護者を支える取り組みなど、地域を盛り上げる力があることも改めて感じました。
●PTA会費は「自分の子のため」ではなく「すべての子どもたちのため」である、という説明の必要性も印象的でした
●PTAは子供のためにどう活動すべきか、という基本的な視点が大事であることを改めて認識しました。
●改めてPTAのことについて考える時間となりました。「ともに子どもたちを支援する大人同士のつながり」がPTAだと思います。単位PTAがPTA’Sのような意識・立ち位置であればいいのかなと思いました。
●PTA活動は、当事者の保護者にとりましては(高等学校では)3年間という限られた期間での活動です。このように限られた期間での活動であるからこそ、対話による協働と継承が大切なのだと教えられました。我が子のみならず、地域の子供の成長を考えていくことができる組織を構築するように、他校の事例を参考にさせていただきます。また、限られた期間といえば、教職員も異動を伴うので、当該勤務校にいる期間で完結するのではなく、自校の好事例を他校にも継承しなくてはならないと思います。そのためにも、学校や地域の魅力や個性を発揮しつつ、学校としての在り方を共有できればよいと思いました。
●そこに住む人たちでビジョンを共有し、子どもたちに何ができるか、何をしたいか、対等な対話の場が必要なんだと考えさせられました。
●教育は先生たちの仕事、も、まちがいではないのでしょうが、先生たちだけに任せることが教育のあるべき姿なのか。実際、現場には無理が生じているところもあるし、地域だけで、PTAの活動でも無理が生じているところも見受けられる。多くを求める前に、何を目指し、何を行い、何を変えて、何を削っていくのか。一度じっくりと考え、対話する機会をつくることが、今後ひとまずやってみたいことなのかもしれない。
●今、本校では、PTAのあり方を根本から見直そうと動き出しています。今は、役員さんとの対話を経て、全保護者に改革案についてのアンケートを実施中です。改革の根本は、「子ども達が明日も来たくなる学校にするために、できることをできる人がやれるPTA」です。これまでのPTA活動は、強制的に役員にさせられ、前例踏襲の活動をやらなければならないからやる・・・というもので、役員のなり手もおらず、年度当初の役員決めはお互いに押し付け合いをする険悪な時間が流れる最悪な会議になっていました。そんなPTAなので、教員にとっても負担でしかないものです。でも、今日のお話にあったように、本来PTAは、子どもにとって必要だと思うことを「協働」してくれる頼もしい味方のはずです。これからの学校は、保護者のみなさんと学校とさらには地域のみなさんと、子どもにかかわるみんなで子どもを育てる場所でありたいと思います。その思いをより強くできた時間でした。ありがとうございました。
●中教審の答申について理解が上がりました。主体的に取り組む多様な団体等の研修が対象になりうることを文部科学省の考えがわかりました。文部科学省の答申にこう書いてあると言うことを地教委等に言っていくことが大切と思いました。
●PTAと学校も自身の立場からの意見だけでなく、子どもを真ん中に置いた対話の場が重要だと感じました。
●勤務校では、まさに本日も仰ったように、PTA活動の企画内容以前に、役員会での人と人の関係性の間に入って話しを聞くことに今年度1学期は大半の時間を費やすことなりました。これは生徒との関わりでも同じで、授業内容に入る以前に、人間関係の部分での教室内の心理的安全性が先に求められることに似ているかなと思います。生徒の場合も保護者様の場合も、年度によって何が起きるか分からない、「何でも起きる」のが学校であると、先日のある研修会でも学び、色々起きる年度はこの置かれた環境でのベストをそれぞれが尽くしていくべきかなと思いました。
先生方に、その声は届いていますでしょうか?
PTA’S(ピータス)には、「先生へ」というコンテンツもあります。
是非、PTAと対話をしながら、必要に応じてピータスもご利用いただきつつ、先生方の負担を軽くしてください。そして、本来の業務に注力してください。
子ども達の豊かな学校生活と、先生方の働き甲斐のために、少しでもお役に立てましたら幸いです。🍀
\その他、PTA’S(ピータス)の「PTA’S代表による執筆・研修・講演実績」は、こちらからご覧ください/



